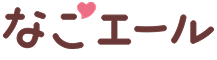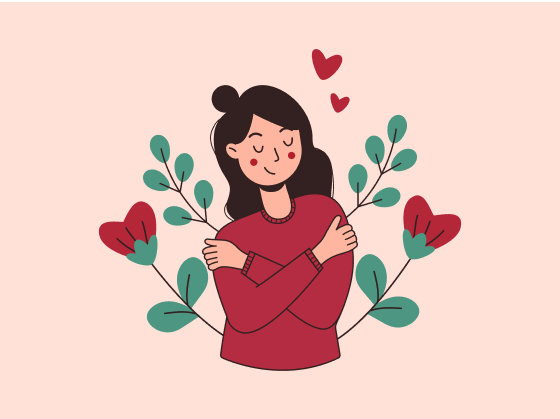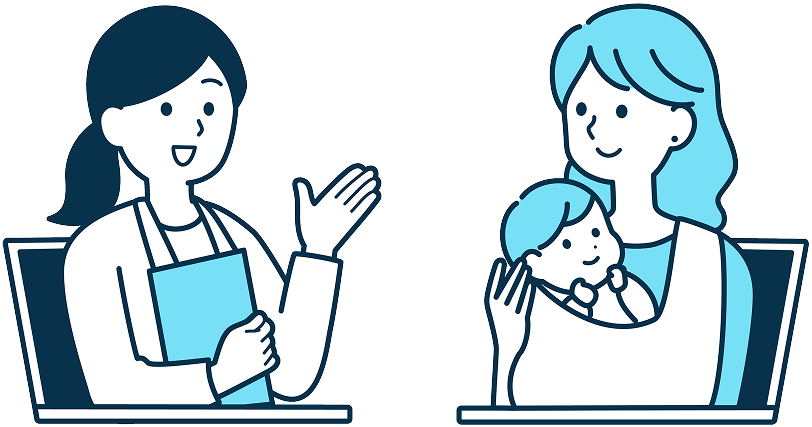下痢・便秘
下痢・便秘は「病気」なの?
「なんとなくお腹の調子が悪い」「便が出ない」「急にトイレに駆け込む」——そんな経験、誰にでもあるのではないでしょうか。下痢や便秘は一時的な不調として見過ごされがちですが、慢性的に続く場合は、体のサインとして受け止めるべき「症状」であり、時には病気の一部でもあります。特に女性は、ホルモンの影響や生活習慣、ストレスなどが腸の働きに影響しやすく、便通の悩みを抱える方が多いのが現状です。
どのようなときに注意したらいいの?
下痢で気を付ける症状は以下のようなものです。
- 水様性の便が頻繁に出る
- 腹痛や腹部の不快感
- 急な便意、トイレに間に合わない
- 食後すぐに便意を感じる
- 発熱や吐き気を伴うこともある
急性の下痢は感染症や食中毒が原因であることが多く、数日で治まることもありますが、慢性的な下痢は過敏性腸症候群(IBS)や炎症性腸疾患(IBD)などの可能性もあります。
便秘で気を付ける症状は以下のようなものです。
- 3日以上排便がない
- 排便しても残便感がある
- 硬くて出にくい便
- 腹部の張りや不快感
- 肌荒れや食欲不振を伴う
便秘は「出ないこと」だけでなく、「出しにくい」「すっきりしない」なども含まれます。慢性化すると、痔や腸閉塞などの合併症を引き起こすこともあります。
なにが原因なの?
下痢の原因は以下のようなものです。
- 細菌やウイルスによる感染(食中毒、ノロウイルスなど)
- 食物アレルギーや不耐症(乳糖不耐症など)
- ストレスや緊張による自律神経の乱れ
- 薬の副作用(抗菌薬、下剤など)
- 過敏性腸症候群(IBS)
- 炎症性腸疾患(IBD:潰瘍性大腸炎、クローン病)
便秘の原因は以下のようなものです。
- 食物繊維や水分の不足
- 運動不足
- 排便習慣の乱れ(我慢する、時間がないなど)
- ストレスや不安
- ホルモンの変化(生理前、更年期など)
- 薬の副作用(鉄剤、鎮痛薬など)
- 腸の病気(大腸がん、腸閉塞など)
女性は月経周期や妊娠、更年期など、ホルモンの変動が腸の動きに影響するため、便通の不調が起こりやすい傾向があります。
どのように対処・予防したらいいの?
下痢に対処するには、日常生活の中でちょっとした工夫が大切です。
- 水分補給をしっかりと:脱水を防ぐため、経口補水液やスポーツドリンクが有効
- 消化に良い食事を心がける:おかゆ、うどん、バナナなどが適しています
- 刺激物を避ける:アルコール、カフェイン、脂っこい食事は控える
- 腸内環境を整える:乳酸菌やビフィズス菌を含む食品(ヨーグルト、味噌など)を摂取
- ストレスケア:リラックスする時間を持つことで自律神経の安定につながります
便秘を予防するには、以下のようなことを心がけましょう。
- 食物繊維を意識的に摂る:野菜、果物、海藻、豆類など
- 水分をこまめに摂取:1日1.5〜2Lを目安に
- 適度な運動を習慣に:ウォーキングやストレッチが腸の動きを促進
- 排便習慣を整える:毎朝トイレに座る習慣をつける
- 腸内環境の改善:発酵食品やプロバイオティクスの摂取が効果的
便秘は「出す力」と「出すタイミング」の両方が関係します。生活リズムを整えることが、腸のリズムを整える第一歩です。
どのようなときに受診したらいいの?
以下のような症状がある場合は、医療機関への受診をおすすめします。
- 下痢が3日以上続く
- 血便や黒色便が出る
- 発熱や激しい腹痛を伴う
- 便秘が1週間以上続く
- 排便時に強い痛みがある
- 便秘と下痢を繰り返す
- 急激な体重減少がある
特に40歳以上の方や、家族に大腸がんの既往がある方は、便通異常が病気のサインである可能性もあるため、早めの受診が重要です。
検査や治療はどのように行うの?
医療機関では、以下のような検査が行われます。
- 問診・視診・触診:生活習慣や症状の確認
- 血液検査:炎症や感染の有無を確認
- 便検査:細菌やウイルス、潜血の有無
- 腹部超音波・CT検査:腸の状態や異常の有無
- 大腸内視鏡検査:ポリープやがんの有無を確認
治療には以下のようなものがあります。
薬物療法
- 下痢:整腸剤、止瀉薬、抗菌薬(感染性の場合)
- 便秘:緩下剤、浸透圧性下剤、刺激性下剤など
- 生活習慣の改善:食事、運動、ストレス管理
- 心理的アプローチ:過敏性腸症候群などには認知行動療法が有効な場合も
薬は一時的な対処には有効ですが、根本的な改善には生活習慣の見直しが欠かせません。
まとめ
腸は「第二の脳」とも呼ばれ、心と体の健康に深く関わっています。便通の乱れは、体の不調だけでなく、心のストレスや生活の乱れを映し出す鏡のような存在です。下痢や便秘は、誰にでも起こりうる身近な症状ですが、慢性化すると生活の質を大きく損ないます。だからこそ、「たかが便通」と思わず、自分の体の声に耳を傾けてみてください。「最近、なんとなくお腹の調子が悪い」「便が出ないのが当たり前になっている」——そんな時こそ、生活を見直すチャンスです。腸が整えば、肌も心も整います。あなたの毎日が、もっと軽やかで心地よいものになりますように。
葛飾医療センター